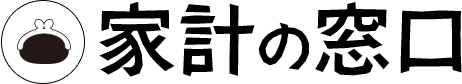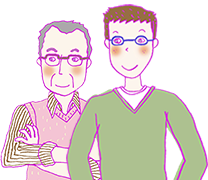決定版☆カンタン家計簿のつけ方

「そもそも、どうして、家計簿をつけないといけないのかしら」
というお悩み・疑問をお持ちの方と一緒に、 家計管理のキホンを確認したいと思います。
さらに、「一番カンタンな家計簿のつけ方」をご紹介いたします。
最終更新日: 2025年6月17日
そもそも、家計簿をつける目的とは?
「家計簿って、つけた方がいいとは思うけど、面倒で続かない……」
そんな声をよく耳にします。では、そもそも家計簿をつける目的とは何でしょうか?
家計改善において、最も大切なのは「現状の把握」です。これは、医師が正しい診断をしなければ適切な治療ができないのと同じ。家計もまた、状況を正確に把握してこそ、適切な改善策(=処方箋)を立てることができます。
たとえば、ファイナンシャル・プランナー(FP)のもとに「とにかくお金に困っています。何とかしてください!」とご相談に来られても、収入と支出の内訳が分からない状態では、具体的なアドバイスが難しいのが実情です。
私たちFPは、「家にはお金がありません」という言葉ほど主観的なものはない、と考えています。というのも、「お金がない」と言う方の資産状況は、実にさまざまだからです。
「お金がない」の真実は人それぞれ
これまでの相談経験では、自己破産寸前の多重債務の方から、金融資産7,000万円以上をお持ちの方まで、「お金がない」と感じている理由は千差万別でした。例えば、資産7,000万円の方は、将来の医療費・介護費・子どもへの援助・年金不安など、長期的な支出を見越して「安心できるお金ではない」と感じておられました。
一方、自己破産寸前の方は、多重債務状態で、 もうあと数ヶ月で住宅ローンの返済は不可能になり、 転がり落ちる寸前まできておられるのに、 月々の収支を、正しく把握しておられませんでした。多重債務数百万円で、自己破産カウントダウン状態の人と、 資産7,000万円の人では、処方箋は全く変わってくるのは ご理解いただけると思います。
同じ「お金がない」という言葉でも、状況が全く違えば、当然ながら取るべき対策も異なります。そのためにはまず、自分の家計の「現実」を知ることが何よりも大切です。
家計簿は現状把握のためのツール
家計改善の第一歩は、「資産状況」と「月々の収支」を把握すること。そのために必要なのが、家計簿です。
実は、家計改善に必要な情報のうち、8割はこの「現状把握」によって得られると私たちは考えています。現状分析に必要な情報を正確に集めることが、 最適な処方箋を出すための8割を占める、 といっても言い過ぎではないと、私たちFPは考えております。
「何から手をつけたら良いか分からない」という方こそ、今日から家計簿を始めてみましょう。
挫折しないための家計簿のコツ
とはいっても、市販されている家計簿ノートは、 相当根性がある人しか続かないと思います。 恥ずかしながら筆者も続きませんでした(>_<)
挫折してしまう理由は、次のような点にあると考えています。
・費目が細かすぎる
(どの費目に分けるかで迷い、時間がとられてしまう)
・毎日や毎週つけるような仕組みになっていて続かない
(つけないと仕事が残っている感じがして、精神的ストレスになる。また結構な時間が取られてしまう)
・合計を手計算しないといけない。
(タテヨコ計算が合わないと気持ち悪く、時間がとられてしまう)集計が手計算で手間がかかる
このように、時間と手間がかかる作業は、気軽に続けられるものではありません。
一方、最近では家計簿アプリや資産管理ツールを活用している方も増えてきました。レシートを写メするだけでアプリが集計してくれるものや、登録した銀行口座や証券口座の資金がリアルタイムで把握でき、見やすくグラフ化してくれるものもあります。ただ、これらのアプリやツールを使っている人が必ずしもやりくり上手と言う訳ではないようです。表やグラフを眺めることで満足してしまい、家計改善は実践できていないケースも見受けられます。家計改善ポイントを発見するには、自分で計算した「手触りのある数字」を眺めることが必要なのかもしれません。
月1回でOK!無理なく続く家計簿のつけ方
そこで、フツーにめんどくさいという感覚を持っている方でも気軽に続けられる、シンプルで効果的な家計簿のつけ方をご紹介します。節約を徹底したい方でなければ、この方法で十分です。
カンタン家計簿のポイント:月1回の簡単集計
1.管理するのは「現金支出」だけでOK!
毎月決まって出ていくお金(家賃・光熱費・保険など)は、口座引き落としで管理できるので、それ以外の「現金支出」のみを対象にしましょう
2.レシートを1ヶ月分集めておく
現金支出のほとんどはレシート・領収書で残ります。忘れずに受け取って、財布や封筒に保管しておきましょう。交通系ICカードなどのチャージも、領収書を発行すれば記録の手間が省けます。 レシートが無いものに関しては、 手帳などにメモをしておきましょう。 月に3,000円以上の漏れがないように といった軽めの程度でがんばりましょう
3.月末にエイヤッと集計作業!
レシートを1ヶ月分集めておいたら、 月に1度、エイヤッと集計作業をします。レシートを費目ごとに分けて、ざっくり合計します。費目の分類はざっくりでOK。金額を記録したら、レシートは捨てて構いません!
余談ですが、家計簿相談があったときに、 「レシートは記録したら、捨てていいですよ」 とお伝えすると、みなさん、すごく喜ばれます☆ レシートをどうするかも、家計簿が気重になる原因のひとつですね。(注:確定申告が必要な方は、経費になりそうなものは、捨てないでくださいね)
おすすめの費目(例)
費目例を、以下にご紹介します。なるべく少ない費目数にするのが続けるコツです。分けて記録しておくと分析しやすいものです。 家計の事情に合わせて、自由に決めてください。
・食費
・外食費
・日用品
・夫のお小遣い
・妻のお小遣い
・子ども費
・教育費
・交通費
・医療費
・レジャー・娯楽費
・特別支出(使い道をメモしておく)
その他、自動引き落としの項目は記帳を見て、 転記すればOKです。 エクセルで表を作れば、計算の手間も省けるのでお勧めです。
できればご主人やお子さんも巻き込んで、家族でワイワイ集計すると楽しく続けられます。
「えー、ママだけケーキ食べてる!」「今月、ゲーム3本も買ってるよ〜」など、笑いも交えながら支出の見直しができます。
家計簿で“家計のモヤモヤ”をスッキリ
月に一度、1時間程度の作業で、家計の見通しがグッと明確になります。節約ポイントも自然と見えてきて、「このままでよいのか?」という漠然とした不安が解消されるはずです。
ライフプラン作成で、さらなる安心を
FPフローリストでは、経験豊富なファイナンシャル・プランナーが、一人ひとりに合ったライフプランをご提案しています。家計簿で日々の管理を整えたら、今度は中長期的な「お金の計画」へ。住宅購入・教育資金・老後の備えなど、ライフイベントに向けた貯蓄の目標やペースも、シミュレーションによって一目瞭然です。
「将来に向けて、今の家計で大丈夫?」
そんな不安がある方は、ぜひ一度、FPフローリストのFPにご相談ください。
このコラムの著者
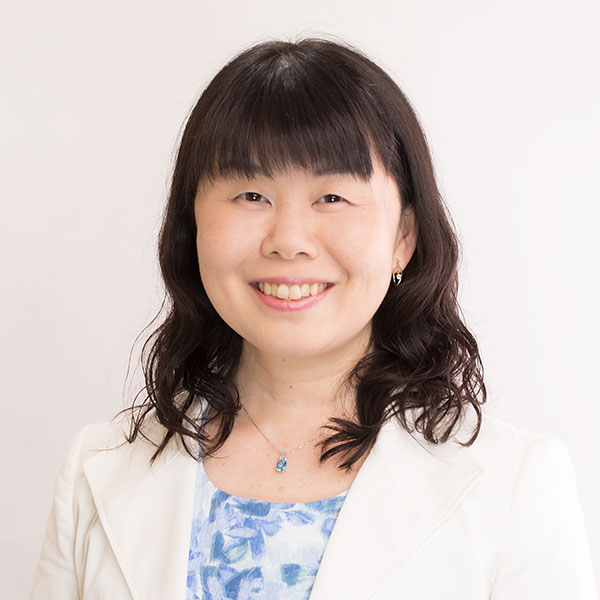
ゆりもと ひろみ
日本を元気にします!
- CFP®認定者
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 宅地建物取引士
- 一種外務員
プロフィール
大阪府出身。1995年神戸大学理学部地球科学科卒業(現地球惑星科学科)
出産を機にマネープランの必要性を痛感し、FP(ファイナンシャル・プランナー)となる。一男一女の子育てをしながら、 開業以来1,200件以上のFP相談を受ける。資産運用・家計管理・住宅購入・保険見直しなど幅広いマネー相談に精通し、働くママとして奮闘する経験を生かした、親身なアドバイスが好評。 2013年「株式会社FPフローリスト」を設立し、社長向けFPコンサルや従業員向けFP相談サービスを開始。日々良質のFPサービスの普及に尽力している。
執筆取材
日経新聞 / 東京新聞 / テレビ東京(ワールドビジネスサテライト) / BS日テレ / フジテレビ(FNNスーパーニュース) / 文藝春秋社(文藝春秋) / プレジデント社/宝島社(リンネル) / 日本FP協会/日本金融通信社/楽天証券(トウシル) / リクルート(SUUMO) / 大創出版(家計ノート) / 学研 / 全国共済 / 一般財団法人教職員生涯福祉財団 他多数
講師講演
北海道水産報徳会 / 首都高速道路労働組合/NEC労働組合 / 日研フード株式会社 / 日本フイルター株式会社/厚木市教育委員会 / 高相建設業組合 他
その他
- 株式会社FPフローリスト 代表取締役社長
- 教育費や家計、資産運用などの疑問はFPに相談して解決しよう!