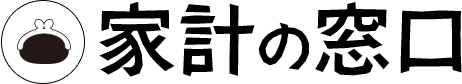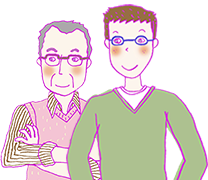資産運用はいつまで続けるべき?やめるタイミングと注意点

第5限 資産運用はいつやめたらいいの?
Q.つみたて投資をしてみたいけれど、どんな商品を選べばよいのでしょうか? また、資産運用をやめるのはどんなタイミングですか?
資産運用を始める前に確認したいこと
資産運用は、資産状況やライフプランによって適した方法や商品が異なります。そのため、これから投資を始めたい方は、まずはご自身の資産状況や将来の生活設計について、ファイナンシャル・プランナー(FP)兼IFAなどの専門家に相談するのがおすすめです。
例えば、投資信託なら月1,000円などの少額からつみたて投資を始められますが、不動産投資となるとある程度まとまった資金が必要になります。「使える資金」とは単に手元にあるお金ではなく、将来の支出予定も加味して考えるべきものです。
基本的には、余裕資金で運用を行うことが原則です。大きく分けると、
資産形成期でまだ余裕資金が少ない方:つみたて投資
まとまった資金がある方:一括投資
が適している傾向があります。ただし、一括で投資する場合はリスクもリターンも大きくなるため、一括+つみたてなどの分割投資でリスクを調整する方法も有効です。
つみたて投資に向いている商品は?
つみたて投資に向いている代表的な商品は「投資信託」です。少額から始められ、運用のプロが投資先を選定・運用します。投資信託は大きく分けて次の2種類があります。
インデックスファンド:日経平均株価やTOPIXなどの株価指数に連動して運用
アクティブファンド:株価指数以上のリターンを目指して運用
初心者の方は、インデックスファンドから始めるとよいでしょう。株価指数以上の大きなリターンは期待しづらいものの、内容が比較的シンプルで幅広い銘柄に分散投資でき、コストが低めに設定されているものが多いです。ただし、ファンドごとに投資対象やリスクの水準は異なりますのでご自身の投資目的やリスク許容度に応じて検討することが重要です。
また、NISA制度を活用すれば、対象商品で得た利益が非課税になるという大きなメリットがあります。NISA対象となっている投資信託を選ぶことで、非課税制度を活用したつみたて投資を行うことができます。
資産運用をやめるのはどんなとき?
運用をやめるタイミングは、ライフプランや資産状況、リスク許容度の変化によって異なります。以下のようなケースが「やめ時」または「見直し時」となることが多いです。
1.目標額に達したとき
たとえば老後資金の準備が目的の場合、目標額に到達した時点で、運用を続けるかの方針を見直すタイミングといえるでしょう。資産運用には増える可能性と同時に減るリスクもあるため、目的を果たした段階で運用をやめることも一つの選択肢です。
2.大きなライフイベントがあったとき
結婚・出産・住宅購入・退職・病気などで、健康状態や生活環境に大きな変化があったときは、運用方針を見直すべきタイミングです。投資に回す余裕資金が減ったり、運用中の資産を取り崩す必要が出てきたりすることもあります。
3.制度変更があったとき
たとえばNISA制度は、非課税枠や期間などがこれまでにも改正されています。制度が有利に変わることもあれば、不利に変わることもあり得ます。こうした制度変更があった場合には、運用方針の再検討が必要になります。
無理なく資産運用をやめる方法
資産運用は、続ければリターンのチャンスがありますが、当然リスクも伴います。一方で、完全にやめると今後の増加の可能性はなくなります。そのため、資産運用のやめ方にも計画性が必要です。以下の3つの方法があります。
① リスク商品から完全に撤退
すべての資産を預貯金や金利収入の確実な商品へ移す方法です。リスクを取らず、安全第一で資産を守りたい方に向いています。
② 徐々にローリスク商品へシフト
株式中心だった投資信託を、債券中心の商品へと数年かけて移行する方法です。リスクを段階的に減らすことで、急な値下がりを避けながら運用を終了できます。
③ 運用を続けながら定期的に売却
つみたて投資の「逆」を行うイメージで、毎月一定額または一定割合ずつ売却し、現金化していく方法です。一部の証券会社で設定可能です。
多くの方は、②と③を組み合わせて、**数年かけて①の状態(リスク商品から全額撤退)**に移行していく方法を選ばれます。
最後に
つみたて投資に限らず、資産運用は「目的」と「生活状況」に合わせて、その方法ややめ方を柔軟に見直していくことが大切です。FPフローリストでは、お客様の個別のライフプランに基づいて、適切な運用方法ややめ方をご提案しています。
「今の資産運用が自分に合っているか知りたい」
「リスクの少ない運用に切り替えたいけれど、将来の資金は大丈夫?」
そんなお悩みがある方は、ぜひFPフローリストのFP相談をご活用ください。
株式会社FPフローリスト 金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第717号
【投資信託の取引にかかるリスク】
投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、申込手数料等の費用が異なり、多岐にわたりますので、詳細につきましては、それぞれの投資信託の「目論見書」「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
・主な投資対象が国内株式
組み入れた株式の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。・主な投資対象が円建て公社債
金利の変動等による組み入れ債券の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
・主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているもの
組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
【投資信託の取引にかかる費用】
投資信託へのご投資には、所属金融商品取引業者等およびファンドごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費等をご負担いただく場合があります。(手数料等の具体的上限額および計算方法の概要は所属金融商品取引業者等およびファンドごとに異なるため本書面では表示することができません。)
・お買付時にお客様に直接ご負担いただく主な費用
「買付手数料」:所属金融商品取引業者等、ファンドによって異なります。
・保有期間中に間接的にご負担いただく主な費用
「ファンドの管理費用(含む信託報酬)」:ファンドによって異なります。
・ご換金時にお客様に直接ご負担いただく主な費用
「信託財産留保額」「換金手数料」:ファンドによって異なります。
買付・換金手数料、ファンドの管理費用(含む信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。各商品のお取引にあたっては、当該商品の目論見書をお渡ししますので必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
このコラムの著者
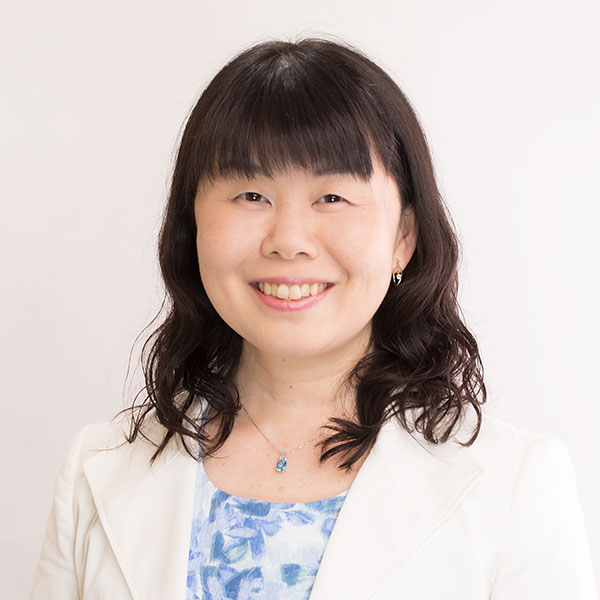
ゆりもと ひろみ
日本を元気にします!
- CFP®認定者
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 宅地建物取引士
- 一種外務員
プロフィール
大阪府出身。1995年神戸大学理学部地球科学科卒業(現地球惑星科学科)
出産を機にマネープランの必要性を痛感し、FP(ファイナンシャル・プランナー)となる。一男一女の子育てをしながら、 開業以来1,200件以上のFP相談を受ける。資産運用・家計管理・住宅購入・保険見直しなど幅広いマネー相談に精通し、働くママとして奮闘する経験を生かした、親身なアドバイスが好評。 2013年「株式会社FPフローリスト」を設立し、社長向けFPコンサルや従業員向けFP相談サービスを開始。日々良質のFPサービスの普及に尽力している。
執筆取材
日経新聞 / 東京新聞 / テレビ東京(ワールドビジネスサテライト) / BS日テレ / フジテレビ(FNNスーパーニュース) / 文藝春秋社(文藝春秋) / プレジデント社/宝島社(リンネル) / 日本FP協会/日本金融通信社/楽天証券(トウシル) / リクルート(SUUMO) / 大創出版(家計ノート) / 学研 / 全国共済 / 一般財団法人教職員生涯福祉財団 他多数
講師講演
北海道水産報徳会 / 首都高速道路労働組合/NEC労働組合 / 日研フード株式会社 / 日本フイルター株式会社/厚木市教育委員会 / 高相建設業組合 他
その他
- 株式会社FPフローリスト 代表取締役社長
- 教育費や家計、資産運用などの疑問はFPに相談して解決しよう!